子どもの進学費用をどう準備するか。親にとって大きな悩みのひとつですよね。
わが家は双子が大学に進学し、給付型・貸与型(金利あり)の奨学金を利用しました。その返還がいよいよ始まるというタイミングで、あらためて「国の給付型奨学金」について調べ直し、これから奨学金を利用する方のお役に立てればと思います。
この記事では、これからお子さんが進学を控えているご家庭に向けて、 給付型奨学金の3つの基準(学力基準・家計基準・資産基準) を親目線でわかりやすく整理しました。
同じように悩む方の参考になれば嬉しいです。
1. 国の給付型奨学金とは?
日本学生支援機構(JASSO)が実施している奨学金には大きく分けて
- 貸与型(借りて返す奨学金・1種:金利ありタイプ/2種:金利なしタイプ)
- 給付型(返さなくていい奨学金)
の2種類があります。
※給付型に採用されると、貸与型の金利無しと併用できる限度額が下がります。その時は金利ありの貸与を借ります
給付型奨学金は、経済的に困難な家庭の学生を支援するための制度で、2020年度から本格導入されました。返済不要で、入学金・授業料の免除/減額もセットで受けられるのが大きな特徴です。
ただし、対象となるには 「学力基準」「家計基準」「資産基準」 の3つを満たす必要があります。
※R6年度より多子世帯に属する場合も支援要件を満たす場合があります(区分4)
2. 学力基準
「成績が優秀でないと受けられないのでは?」と不安になる方もいますが、給付型奨学金の学力基準は思ったよりも柔軟です。
高校から進学する場合
- 高校の評定平均が 3.5以上
- ただし、学業に意欲があり、進学先で学ぶ意思があると学校長が認めれば、3.5未満でも推薦可能
大学・専門学校在学中に申請する場合
- 修得した単位数が標準単位数以上
- GPA(成績評価係数)が 在学学部における上位2分の1の範囲に属すること
👉 親として意識したいのは、「絶対的な学力」よりも「継続して勉強」する姿勢が重視されるという点です。娘の1人が、単位を落としGPAが下がり警告文書が届きました。奨学金が止まるかもとヒヤヒヤしました💦
3. 家計基準
最も重要なのが家計基準です。給付型奨学金は 住民税情報を基準に判定されます。
支援の区分と内容
| 区分 | 収入基準(申込本人・生計維持者) | 支援内容(私立の場合) |
|---|---|---|
| 区分Ⅰ | 市町村民税所得割が非課税 | 授業料70万免除・入学金26万免除+給付金満額75,800円 |
| 区分Ⅱ | 支給算定基準額100~25,600円未満 | 授業料・入学金区分Ⅰの2/3免除+給付金2/3 |
| 区分Ⅲ | 支給算定基準額25,600~51,300円未満 | 授業料・入学金区分Ⅰの1/3免除+給付金1/3 |
年収の目安(給与収入ベース)
※扶養人数によって変わります
- 夫婦+子ども2人 → 約270万円程度まで対象
- シングルマザー+子ども2人 → 約200万円程度まで対象
👉JASSOの「進学資金シュミレーター」でおおよその 目安として確認できますのでお試し下さい。実際には 所得控除(iDeCo・社会保険料・医療費控除など) がどれだけあるか、世帯構成で結果が変わります。
4. 資産基準
見落としがちですが、給付型奨学金には「資産基準」もあります。
- 申し込み時点で申し込み本人と生計維持者の預貯金や株式などの金融資産が5,000万円以内であること
👉 預貯金だけでなく、NISA・株式や投資信託も対象になるので注意が必要です。
5. 親としての体験談
我が家は、給付型を第Ⅰ区分で入学金・授業料免除・給付型の奨学金を頂けました。
ただ、2人とも私立大学に進学したのでそれでも足りません。
更に実家を出て、都心付近に2人とも一人暮らし💦泣けます
子供が小さいうちからあらゆる可能性を考えておきたいものです。
iDeCoを活用して、課税所得を下げられ、非課税に近づけるかもしれません。
それを考えると、早めに「どの控除を使えるか」を調べておくべきだと思います。
今、双子の奨学金返還を3等分して私も一緒に返しますが、借りすぎないことが大事です。
6. まとめ
国の給付型奨学金は、
- 学力基準:高校評定3.5以上(または学ぶ意欲)/修得単位数が基準単位以上+GPAが在学学部のおける上位2分の1の範囲に属すること
- 家計基準:住民税非課税世帯~生計維持者と申込本人の支給額算定基準額の合計51,300円未満であること
- 資産基準:生計維持者と申込本人の金融資産が5,000万満未満
という3つの条件を満たすことで利用できます。
子どもの未来を支える制度ですが、実際には知らずに借りすぎて返済に苦しむ家庭も多いのが現実です。我が家もそのくちです。
親としては「借りる前に、奨学金について、給付型の可能性を徹底的に調べること」が本当に大切だと思います。
少しでも貯金しておくことも大事です。お子さんが小さいならNISAで用意したいですね。
これから奨学金を検討するご家庭には、ぜひ早めに市町村の課税証明書や資産状況を確認し、制度をうまく活用していただきたいです🌻





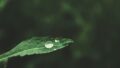

コメント